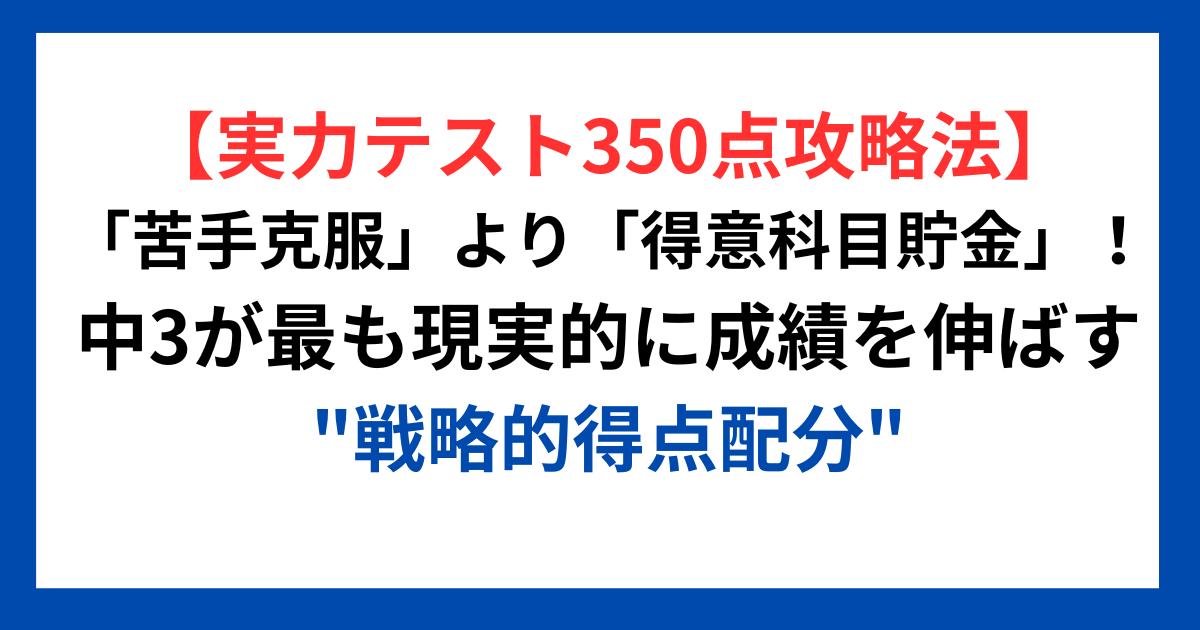
【実力テスト350点攻略法】「苦手克服」より「得意科目貯金」!中3が最も現実的に成績を伸ばす"戦略的得点配分"
2025年10月11日 08:37
目指せ350点!
オール70点の壁を破る
「がんばることが、ちょっと好きになる」STEP式ロードマップ。
「高校受験に向けて、実力テストで5教科350点を目指したい!」
きっと今、そう強く思っている中3生と保護者の方は多いでしょう。
でも、こんな風に考えていませんか?
「350点ってことは、全科目70点取らなきゃいけないんだよね…」
「一番の苦手科目の点数を一気に上げないと、間に合わないかも…」
真面目ながんばり屋さんほど、「すべてを平均点以上に」と意気込みがちです。
ですが、結論から言います。
その方法では、多くの場合、最短距離で350点には到達できません。
私たちSTEP教育学館では、この時期の受験生を見ていて「がんばり方がもったいない!」と感じることがあります。
本記事では、努力が無駄にならない「戦略的得点配分」の考え方をご紹介します。
苦手科目で無理しない。
得意科目で確実に貯金する。
この現実的なアプローチこそが、中3の残り半年で最も再現性が高く、350点を超えるためのSTEP式ロードマップです。
この記事を読めば、あなたの努力が点数に結びつき、「がんばることが、ちょっと好きになる」状態を目指せます。
1. なぜ「全科目70点」はリスキーなのか?
1-1. 先生もあなたも「全科目得意」はありえない
まず、指導している先生を含め5教科すべてが得意科目という人はいません。
得意・不得意があるのは当然です。
苦手科目が50点だとします。
これをいきなり70点まで20点伸ばすには、基礎を固め直し、応用問題に手を出せるようになるほどの時間と労力が必要です。
これは、受験までの限られた時間においては、事実上困難です。
1-2. 非現実的な目標は「がんばる意欲」を削ぐ
苦手科目に膨大な時間を費やしても、なかなか成果が出ないと、「がんばっているのに伸びない…」と自信を失い、受験勉強全体への意欲が低下してしまいます。
「がんばることが、ちょっと好きになる」ためには、成果が見える成功体験が必要です。
2. STEP式「戦略的得点配分」の超現実的な考え方
目指すのは合計350点。
2-1. 【STEP1】現実的目標は「苦手60点、得意80点」
目標点数を
70点・70点・70点・70点・70点(合計350点)にするのと、
85点・70点・70点・60点・65点(合計350点)にするのと、どちらが現実的に可能でしょうか?
現状50点の科目を70点に上げるより、50点を60点に伸ばす方が、ずっと実現可能です。
苦手科目50点 → 60点: 10点アップ。
まだ実現可能。
得意科目70点 → 80点以上: 10〜15点アップ。これも実現可能です。
平均的に70点をとろうとすると、350点の到達は難しいでしょう。
中には、まんべんなく解ける生徒もいますが、多くの場合、得意科目で「貯金」をする戦略が最も有効です。
2-2. 【STEP2】「10点の伸び」は難易度が違う
苦手科目50点を60点に伸ばすのは、1科目4・5問程度正解数を増やせばよいです。
これは基本問題を確実に取る対策だけで到達できる可能性が高いです。
この小さな成功体験の積み重ねが、お子さまの自己肯定感を高め、全体的な学習意欲を向上させます。
3. 【保護者様へ】親がすべき「声かけ」のSTEP
中3の成績UPの鍵は、「まんべんなく」より「メリハリ」です。
保護者の方は、お子さまの「得意科目」を承認し、自信を深める声かけをしてあげてください。
推奨する声かけ:「〇〇(得意科目)が80点超えたのはすごい!その調子で、〇〇(苦手科目)はあと5問正解を目標にしてみようか」
4. 根拠データ:「苦手克服より得意強化」の成功実例
【実例】 A高校志望 Sくん(中3)
苦手な数学に悩み、総合点が伸び悩んでいました。
STEP式で「得意な英語と理科で85点以上を取る貯金戦略」に切り替えたところ、数学のプレッシャーが減り、全体的な学習効率が向上。
苦手な数学も60点台に乗せることができ、目標の360点を達成。
あなたの「がんばり方」は正しいか?無料診断してみませんか?
ここまで読んでくださった方は、「がんばり方」を見直す準備ができています。
私たちのSTEPメソッドは、単なる勉強法ではありません。「自分だけの勝ちパターン」を見つけ、「がんばることが、ちょっと好きになる」状態をつくるための戦略設計です。